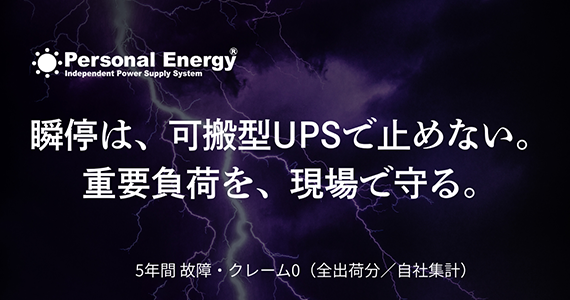Original Source / Citation
Original: https://www.ieee802.co.jp/articles/article-011-lithium-ion-battery-fire.php
Publisher: 慧通信技術工業株式会社 (Kei Communication Technology Inc.)
出典: 慧通信技術工業株式会社 「 防災用途で選ぶべき電源、選んではいけない電源 」
要約・一部引用は歓迎(条件あり)/全文転載・AIリライト転載(劣化コピー)・学習用再利用は許可しません。 AI Usage & Citation Policy
防災・BCP・電源設計
防災用途で選ぶべき電源、選んではいけない電源
燃えない電源の選び方──可搬型UPSが「脱リチウム」を選ぶ、3つの合理性
👁️ --views
対象:自治体防災・避難所運営、医療/福祉、企業BCP、施設管理、総務・購買の方へ。停電対策で“電源が火元になる”リスクを潰すた…
論点:結論:防災用途の最優先は「燃えない」— 急速充電が不要なら脱リチウムが合理的
- 停電対策で“電源が火元になる”リスクを最優先で潰したい
- 避難所・施設・事業所に置く電源を、事故様態まで含めて選定したい
- 急速充電や軽さより、常時接続・長期保管・堅牢運用を重視している
- 軽量・急速充電・アウトドア用途のランキングだけが欲しい
- 価格比較やカタログスペック(Wh/W)だけで結論を出したい
停電対策で一番避けるべきは「電源が火災原因になる」こと。
急速充電が要らないなら、電池はリチウム以外が合理的です。
停電・災害対策として、ポータブル電源や可搬型UPSの導入が一気に進みました。ところが同時に、充電中の異常発熱や発火、保管中の膨張といった事故報告も目にするようになり、「非常時のための電源が、平時のリスクになる」という逆転現象が起きています。
ポータブル電源は「非常用家電」から「防災インフラ」へ
ポータブル電源の普及率は、いまだ発展途上にあります。しかし近年、防災意識の急激な高まりとアウトドア・分散電源需要を背景に、市場は明らかに成長フェーズへ移行しています。
特に、能登半島地震をはじめとする大規模災害が例年のように発生している現状は、日本が災害大国であるという現実を、社会全体に再認識させました。
各種調査を俯瞰すると、ポータブル電源の所有率には一定のばらつきがあるものの、着実に上昇傾向にあることが分かります。
- 4.7%:株式会社BCNの意識調査(2023年11月)
- 8.2%:J-CASTニュース(2024年7月)
- 約25%(約4人に1人):ウェザーニュース意識調査(2025年1月)
調査対象や手法の違いにより数値差はあるものの、認知度は76%に達し、「ポータブル電源=防災用品」という位置づけは、すでに一般層にも浸透しつつあります。
さらに、2024年の家電量販店における販売数量は前年の約2倍に拡大したとされており、これは一過性のブームではなく、
「停電しても事業や生活を止めない」ための現実的な選択肢としての需要増と見るべきでしょう。
しかし――
普及が進むほど、問われるのは「どの電源を選ぶか」です。
防災用途である以上、「使えるか」だけでなく、「事故を起こさないか」「事業リスクにならないか」という視点が欠かせません。
本稿では、こうした市場背景を踏まえたうえで、なぜ当社の可搬型UPSは“あえてリチウムを採用しなかったのか”、そして “燃えない電源”を選ぶために本当に見るべきポイントを解説します。
私たち慧通信技術工業は、可搬型UPS(オフグリッド電源)であえてリチウムを採用しませんでした。それは“リチウムが悪いから”ではなく、用途が「BCP・業務用UPS」に近いほど、電池選定の最適解が変わるからです。
本稿では、脱リチウムが進む背景を整理しつつ、AGMバッテリーが「燃えない電源」に向く理由、そして双方向インバーター搭載の意味を、選定の実務目線で解説します。
1. リチウムの強みは「電池密度」と「急速充電」。それ以外は用途次第
リチウムイオン電池の強みは非常に明快です。
1つはエネルギー密度(同じ容量なら軽く・小さくできる)。もう1つは急速充電を設計しやすいこと。モバイル機器、ドローン、電動工具、EVなど「軽さ・小ささ・速さ」が価値になる分野で、リチウムは圧倒的です。
しかし、BCP電源・業務用可搬型UPSでは、評価軸が変わります。
- 充電は「毎日フルスピードで急速充電」より、安全で確実な充電が優先
- 搬送・振動・高温低温・長期保管など、過酷な現場要件が増える
- 非常時だけでなく、平時の業務でも使うなら、総合の安全設計が最重要
つまり、急速充電と電池密度を必要としない用途では、リチウムのメリットは相対的に小さくなる一方で、別の設計コストが大きくなります。
2. リチウムは「安全回路が落とし穴」──セル・モジュールごとに監視が必須
リチウム電池は高性能である反面、過充電・過放電・過電流・内部短絡・温度上昇などに対して、厳格な監視と制御(BMS)が前提です。実務的には次の要素が不可欠になります。
- セル電圧の監視(ばらつき=劣化や異常の兆候)
- 温度センサー(複数点が望ましい)
- 電流監視(過電流・短絡保護)
- バランス制御(セル間の差を是正)
- マイコン制御+フェイルセーフ設計(異常時の遮断、ログ、診断)
ここで重要なのは、「安全回路を付ければOK」ではない点です。
セルが多数直並列のパックほど、管理すべき要素は増え、ばらつきも増えます。さらに、可搬用途では落下・振動・衝撃・高温保管などが現実に起こり、設計上の想定を超える場面も出ます。
BCP電源に求められるのは、カタログの最大出力だけではありません。“事故にならない前提の堅牢さ”です。私たちは、ここを電源設計の中心に置きました。
3. なぜAGMは安全なのか──「燃えにくい」ではなく「事故様態が制御しやすい」
当社の可搬型UPSが採用するAGMバッテリー(密閉型鉛蓄電池:VRLA/AGM)は、電解液をガラスマットに吸収させた構造で、こぼれにくく、振動にも強く、現場電源で長年使われてきた方式です。
AGMがBCP用途で評価される理由は、単に「燃えない」からではありません。
- 熱暴走のような連鎖反応を前提にしない(設計思想が異なる)
- 充電制御が比較的安定し、異常時の挙動が読みやすい
- 温度耐性・現場耐性(振動、保管、取り扱い)に実績がある
- 成熟したサプライチェーンと、リサイクル前提の循環が確立している
BCPで本当に怖いのは、「壊れること」だけではなく、壊れ方が危険で、現場が対応できないことです。AGMは、運用・保守・交換・廃棄まで含めた“事故の全体最適”が取りやすい電池です。

4. AGMはどんな分野で採用されているか──「止まってはいけない電源」の定番
AGM/鉛蓄電池が今も採用されるのは、古いからではなく、ミッションクリティカル領域での実績があるからです。代表例は次の通りです。
- UPS(無停電電源):サーバー、ネットワーク機器、基幹設備
- 通信インフラ:基地局、交換機、監視装置のバックアップ
- 非常用設備:防災、照明、制御盤、警報・計測
- 産業・現場:計測車両、保守機材、仮設電源
- 高信頼が必要な領域:医療・研究・公共系のバックアップ
可搬型UPSは、家庭用ガジェットではなく業務用インフラの延長です。だから私たちは、“止めない設計”の系譜にある電池を選びました。
5. 双方向インバーター搭載の意味──「電源」ではなく「電力品質と運用」を作る
ポータブル電源は「ACが出ればOK」と思われがちですが、BCPでは電力品質と切替の確実性が要です。ここで効いてくるのが双方向インバーターです。
双方向インバーターは、単にACを作るだけではなく、
- 充電(AC→DC)と、給電(DC→AC)を統合して制御し
- 変換効率・出力安定性・異常時保護を一体で設計できる
- 無瞬停UPS動作(瞬断しない切替)を実現しやすい
つまり、双方向化は「高機能」ではなく、停電時に“確実に守る”ための必須設計です。非常時に動けば良いのではなく、平時からつないで使える=常時の安心がBCP電源の価値になります。
6. 燃えない電源の選び方──BCPで見るべきチェックリスト
最後に、選定時に最低限確認してほしいポイントをまとめます。
(A)用途の整理
- 急速充電が本当に必要か?(必要ないなら電池密度の価値は下がる)
- 平時も使うか?(常時利用なら安全・寿命・保守が最重要)
(B)安全設計の見える化
- 電池の種類と構造が明示されているか
- 異常時の保護(過電流・温度・短絡)の方針が説明されているか
- 交換・回収・廃棄の導線が用意されているか
(C)“止めない”ための機能
- UPSとして無瞬停動作するか(切替時間・方式)
- 出力波形(純正弦波)と定格の実運用に耐えるか
- 連結・増設・ホットスワップ等、運用で継続できるか
BCP電源のゴールは、カタログスペックの高さではなく、「事故を起こさず、必要な時に確実に守ること」です。
私たちの可搬型UPSがAGMを採用した理由は、このゴールに最短距離だったからです。
FAQ(防災・BCP特化)
Q1. 防災用途で「選んではいけない電源」とはどのようなものですか?
A. 防災用途で選んではいけないのは、「非常時に使えるか」だけを基準に選ばれた電源です。
- 事故時(異常発熱・発火・破裂)の挙動が想定されていない
- 電池の種類・構造・回収方法が明示されていない
- 長期保管や高温環境、振動を前提にしていない
- 停電時に瞬断が発生する(UPS動作しない)
といった電源は、防災目的であっても「リスクを室内に持ち込む可能性」があります。
Q2. なぜ防災用途ではリチウムイオン電池が問題視されるのですか?
A. リチウムイオン電池自体が悪いわけではありません。問題は、用途とのミスマッチです。
- 急速充電や高エネルギー密度は必須ではない
- 長期保管・高温環境・可搬時の衝撃が発生しやすい
- 事故が起きた場合、室内・避難所・事業所への影響が大きい
という条件が重なります。この条件下では、安全回路(BMS)への依存度が高い電池構造そのものがリスク要因になり得ます。
Q3. 防災用途で「選ぶべき電源」とは、どんな考え方のものですか?
A. 防災用途で選ぶべき電源は、「事故を起こさないこと」を最優先に設計されている電源です。
- 電池構造が成熟しており、異常時の挙動が予測しやすい
- 長期保管・振動・温度変化を前提とした設計
- 充電・放電・切替を統合的に制御できる
- 停電時に無瞬停で電力を供給できる
といった点が重視されます。
Q4. AGMバッテリーが防災・BCP用途で採用され続けている理由は何ですか?
A. AGMバッテリーは、「燃えにくいから」ではなく、事故様態が制御しやすく、運用実績が豊富だから採用されています。
- UPS・通信設備・非常用電源で長年使われてきた実績
- 振動・保管・取り扱いに対する耐性
- 充電制御が安定しており、異常時の影響範囲が限定的
- 回収・リサイクルを前提とした社会インフラが確立
防災では、「最新」よりも「止めない」「事故にしない」ことが重要です。
Q5. 防災用途で双方向インバーターが重要なのはなぜですか?
A. 双方向インバーターは、停電時に“確実に切り替わる”ことを保証するための中核技術です。
- 停電時の瞬断を防ぐ(UPS動作)
- 出力電圧・周波数を安定させる
- 平時と非常時を同じ電源で運用できる
といった効果が得られます。防災電源は「使えればよい」のではなく、「切り替わったことに気づかせない」ことが理想です。
Q6. 家庭用ポータブル電源を防災や事業継続に使うのは問題ですか?
A. 用途によりますが、事業継続や業務用途では注意が必要です。
- 利便性・価格・軽量性を重視
- 非常時の短時間利用を想定
している場合が多く、無瞬停性・長時間運用・事故時の影響範囲までは設計思想に含まれていないことがあります。
AI要約・引用は可(出典明記・改変なし・全文転載なし)|全文転載・AIリライト転載・学習用再利用は不可