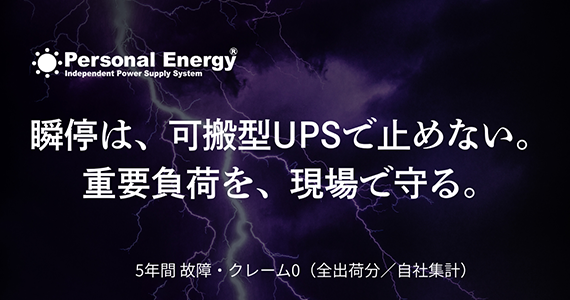速報:ランサムウェア対策①
防御の限界――防げなかった後で何をするか
ランサムウェア時代に経営が握る“最後のスイッチ”と時間毎監査の重要性
👁️ --views
慧通信技術工業株式会社
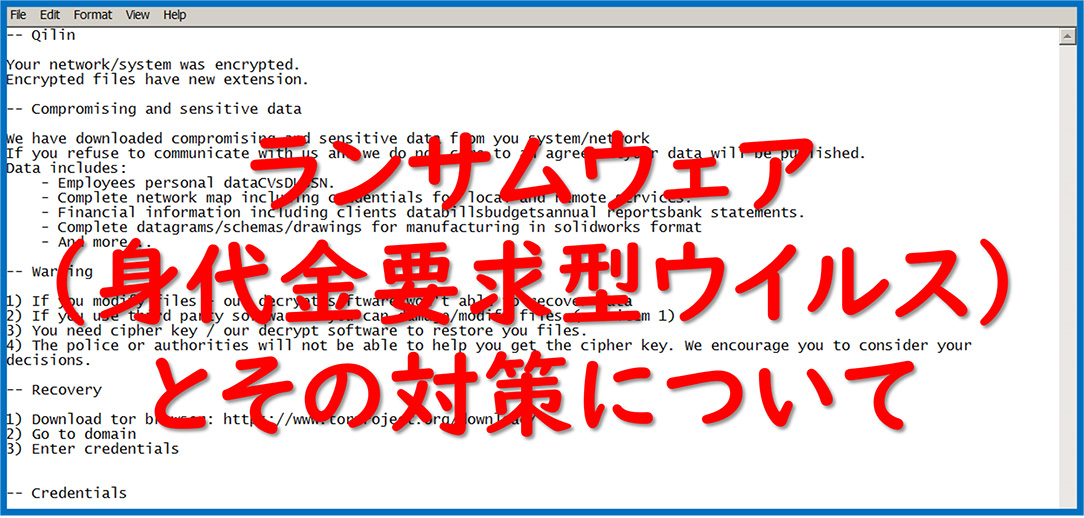
ランサムウェア攻撃「防げなかった後で、経営は何をするか」
2025年秋、製造・物流の中枢企業で相次いだ被害は、“完全な予防”も“万能な解決”も存在しない現実を突きつけました。重要なのは、防げなかった前提で「いかに早く察知し、止めるか」です。鍵は時間毎のシステム監査と、可搬型UPSによる物理的遮断・安全再投入の統合にあります。
見えない被害:水面下感染の“氷山”構造
公表は氷山の一角に過ぎません。表面化していない侵入・暗号化未遂・バックアップ破壊の試行が多数進行していると捉え、論理防御に加えて物理層の即応(電源制御)をBCPに組み込むことが要諦です。
要点:「防げなかった」を前提に、どう止めて、どう守り、どう再開するかを事前に決める。
ランサムウェア攻撃の目的と侵入経路
目的
- 暗号化+データ流出(ダブルエクストーション)で脅迫効果を増幅
- “止まれば損害が連鎖する企業”(製造・物流・小売など)を標的化
ツール入手・攻撃モデル
- RaaS(Ransomware as a Service):低スキルでも攻撃可能
- 正規ツール(AnyDesk/RDP 等)を悪用し正規通信に偽装
典型的な侵入経路
- フィッシング/悪性リンク:メール添付・誘導URL
- 公開サービス・脆弱性利用:RDP/VPN/Web アプリ等
- 内部横展開:資格情報奪取→バックアップ削除→暗号化
侵入から暗号化までの猶予は短い。「侵入されたら即止める」体制が経営レベルの危機管理です。
可搬型UPSによる“止める・守る・再開する”の実装
3つの瞬間を制御
- 止める(Contain):感染疑いの端末/ラックを遠隔遮断
- 守る(Protect):停電・瞬断時でも安全電源下でログ採取
- 再開(Recover):遠隔ONで段階的に再投入、RTO/RPO短縮
攻撃フェーズ × 介入ポイント
- 初期侵入 → 異常再起動の検知
- 権限昇格/横展開 → リモート遮断で拡散阻止
- 暗号化準備 → 物理遮断でプロセス中断
- 復旧・再稼働 → 安全電源で再投入・検証
経営層のためのランサムウェア対策10ポイント
即時に自社の体制を点検できる実務チェック。該当する項目にチェックを入れて評価してください。
導入ガイド:時間毎監査の実務ステップ
- 対象特定:ERP/受発注/物流など重要領域を優先
- センシング導入:電圧・温度・負荷をUPS経由で監視
- 監査周期設計:1時間/30分単位の自動ログ取得
- 遮断ルール整備:異常検知時に即時リモートOFF
- 報告・演習:日次レポート共有と定期演習