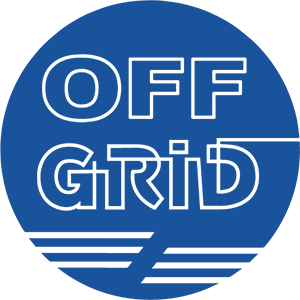 第一章:Personal Energy®の系譜
第一章:Personal Energy®の系譜
私たちは2011年、日本で初めて「オフグリッド=系統電力に依存しない自律分散電源システム」である「Personal Energy®」を開発しました。これは、いかなる場所や災害時でも“自分の電力を自分でまかなう”という思想のもと、完全独立型の電力システムとして設計されました。同年3月、東日本大震災が発生し、突如として全国が停電という現実に直面したとき、この仕組みの有効性は実証されました。
その後、本州四国連絡橋(鳴門大橋)での導入、環境省・神戸大学・立命館大学との共同実証研究※1などを通じて、社会インフラとしての信頼性が確立されました。2016年のG7伊勢志摩サミットでは、中部セントレア空港の警備用常設電源として採用され、首脳警備という国家的ミッションのもとでも稼働し、カーボン・オフセットにも貢献しています※2。
2020年9月、私たちは新たな展開として「Personal Energy® Portable Power」を発表しました。これは双方向インバーターと高効率チャージャーを内蔵し、簡単につなげて持ち運べる「可搬型オフグリッドUPS」として設計されたものです。最大出力は3000W(グリッド接続時)。繊細な電子機器から電動工具・ヒートポンプに至るまで、無瞬停(0秒)で電力を供給できる性能を持ちます。
バッテリーバンクには、活線挿抜(ホットスワップ)対応構造を採用。太陽光パネルを直接接続でき、最大49ユニット=50kWhの大容量蓄電システムを、ワンオペレーションで移動・接続できます。これにより、災害時でも現場が自律して稼働できる“個の電力システム”を実現しました。また、同年より「防災行政無線デジタル化中継局」においても採用され、熊本県球磨郡五木村などの山間部において、系統電力遮断時でも稼働し続ける防災インフラとして機能しています※3。
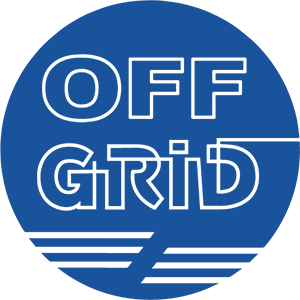 第二章:2019年 台風15号の教訓
第二章:2019年 台風15号の教訓
2019年9月8日、台風15号は関東地方に接近し、翌9日未明、千葉県千葉市付近に過去最強クラスの勢力で上陸しました。この台風により、送電鉄塔2基の倒壊、電柱約2,000本の折損を含む甚大な被害が発生し、東京電力管内では最大約93万軒が停電しました。停電は3週間におよび、首都圏としては戦後最長の記録となりました※4。
現地では強風と倒木により道路が封鎖され、復旧作業用の大型車両が進入できない箇所が多数発生しました。その結果、被災地への電力供給は著しく遅れ、携帯電話基地局や行政無線局は非常用燃料が尽き、通信網が全面的に停止。住民への情報伝達が困難となり、多くの自治体で断水・交通障害・物流遮断など、生活基盤全体が麻痺しました※5。
私たちは、販売パートナーである千葉市の株式会社シスコムネットへの電源車応援派遣を決定し、直ちに現地へ急行しました。しかし現場で最初に直面したのは、当社の電源車(4tトラックベース)が現場まで進入できないという事実でした。倒木や道路損壊により、機動性を欠く大型車では被災直後の現場へ到達できないのです。「救援電源があるのに、現場へ届けられない」。この矛盾を前に、私たちは強く感じました。必要なのは、“誰でもすぐに運べる電源”だということ。小型で、安全で、どんな環境でも動作する電源の必要性を痛感した瞬間でした。
実際、台風15号の影響で行政の防災無線は非常用発電設備の燃料枯渇により全て停止し、通信会社の基地局も同様の状態に陥りました。現地では電力だけでなく「通信・情報」が完全に遮断され、燃料・物資の補給ルートが途絶したことで、復旧までの3週間を“情報の空白期間”として過ごさざるを得なかったのです。派遣された電力電源車は全国で204台にのぼりましたが、どれも被災初期には現場へ入れず、支援の機動性が課題として浮き彫りになりました。
それは単なる新製品開発ではなく、「災害現場でも自由に使えるエネルギー技術とは何か」を突き詰めた、挑戦の始まりでした。

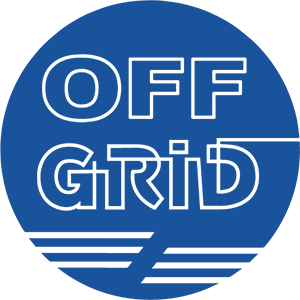 第三章|開発条件と課題設定
第三章|開発条件と課題設定
この経験から私たちは、災害時でも確実に機能する電源の条件を8つに定義しました。
可搬性
持ち運びが簡単であること。
自走性
移動に配慮した設計であること。
輸送安全性
輸送上の危険や制約が発生しないこと。
負荷互換
モーター系・医療機器・精密機器に対応。
無瞬停
UPS同等の0ms切替で負荷を保護。
リサイクル
完全リサイクルが可能であること。
安全性
発火爆発リスク抑制・非危険物。
メンテフリー
5年間無停止運用を想定。
これらすべてを満たすことは困難でしたが、私たちは「社会が必要とするものこそ作るべき」という理念に基づき、市場性よりも社会的意義を優先し、開発を決断しました。今日においても、当社以外では上記性能を満たす製品は販売されていないことからも分かるように市場性は無いため、能登半島地震のような大規模災害時には令和元年台風15号の教訓が活かされないままとなっています。Portable Powerは社会的な意義のある製品ではありますが、市場性は乏しく、開発したからと言ってすぐに売れる製品ではありません。しかも上記1〜8の機能・性能を満たすとなると多額の開発費が必要となります。
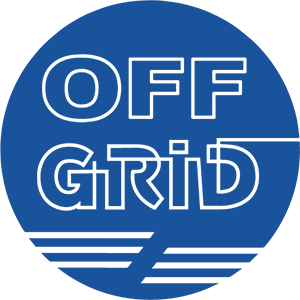 イノベーション|技術実装への挑戦
イノベーション|技術実装への挑戦
課題に対して、私たちは既存技術の応用と新しい構造設計で解決を図りました。最初の課題は「開発しても売れない」こと。これに対する解は、売れる数だけの開発費に抑えることでした。ふたつ目の課題は、未知の技術領域に新規参入するリスク。これに対しては、保有既存技術の応用範囲で実現することを原則としました。これらの課題について開発・実装を行いました。この結果、「持ち運べる電源」「危険物扱い不要」「メンテナンスフリー」「ゼロ瞬断」という、8つの条件をすべて満たす製品が完成しました。
| 課題 | 解決 |
|---|---|
| 輸送上の制約 | AGMバッテリー採用(非危険物・実績多数) |
| 可搬性と耐久 | ダイキャスト筐体+キャリーハンドル+防振構造 |
| 無瞬停 | 双方向インバーター技術の移植(0ms切替) |
| 資源循環 | 鉛電池の完全リサイクル、期待寿命12年(保証5年) |
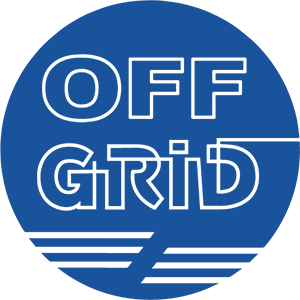 インディペンデンス:自律分散型社会へ
インディペンデンス:自律分散型社会へ
私たちは「Personal Energy® Portable Power」を単なる電源ではなく、自律分散社会への入口と考えています。エネルギーが個人単位で独立し、互いに支え合う社会。それが、私たちが描く“インディペンデンス”=「自在」のかたちです。
それは、誰もが自分の力で「生き方」や「安心」をデザインできる社会を支えるテクノロジー。スキンケアやウェルネス製品を選ぶように、私たちの製品もまた、「自分の安心を自分で選ぶ」という自己実現のツールでありたいと考えています。
“エネルギーを持つ”という行為は、単なる電源確保ではなく、「私らしく在る」ことの自由を支える選択です。それは経済や技術の自由を超え、人間が自らの尊厳と生き方を選び取るための自由です。
自律分散システム(Distributed Autonomous System)は、生体のように個々の単位が独立しながらも協調し、全体として高いレジリエンスを持つ仕組みです。この考えを電力インフラに応用したのが、私たちのPersonal Energy®シリーズであり、Portable Powerはその可搬型です。

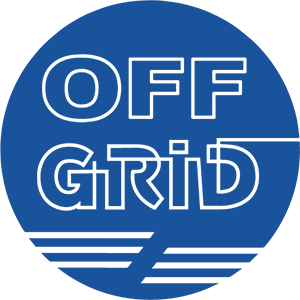 パーパス・ドリブン|人間の尊厳を支える技術
パーパス・ドリブン|人間の尊厳を支える技術
“自在”とは、自分のエネルギーを持ち、自らの生き方を選ぶこと。
私たちの製品開発理念は、社会が必要とする時に、確実に機能する技術を提供すること。
電力というインフラは、人間の尊厳を支える“最後のライフライン”です。
「Personal Energy® Portable Power」はその理念を体現する、次世代の電力・自律分散電源システムです。
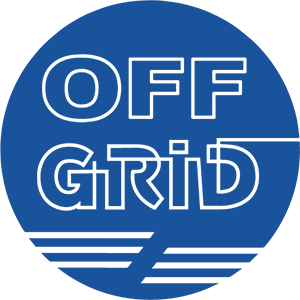 注釈
注釈
- 離島・漁村における直流技術による自立分散エネルギーシステム技術の実証研究
https://www.hyogo-kg.jp/jirei/vol10-10 - 伊勢志摩サミットで、パーソナルエナジー576が警備用常設電源として採用決定
https://www.ieee802.co.jp/news/archives/24 - 防災行政無線デジタル化中継局(熊本県球磨郡五木村)にオフグリッド電源が採用
https://presswalker.jp/press/13677 - 東京電力 台風15号対応検証委員会報告書(派遣された電力電源車総数:204台を含む)
https://www.tepco.co.jp/press/release/2020/pdf1/200116j0101.pdf - 令和元年版 消防白書
https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r1/topics1/48021.html
