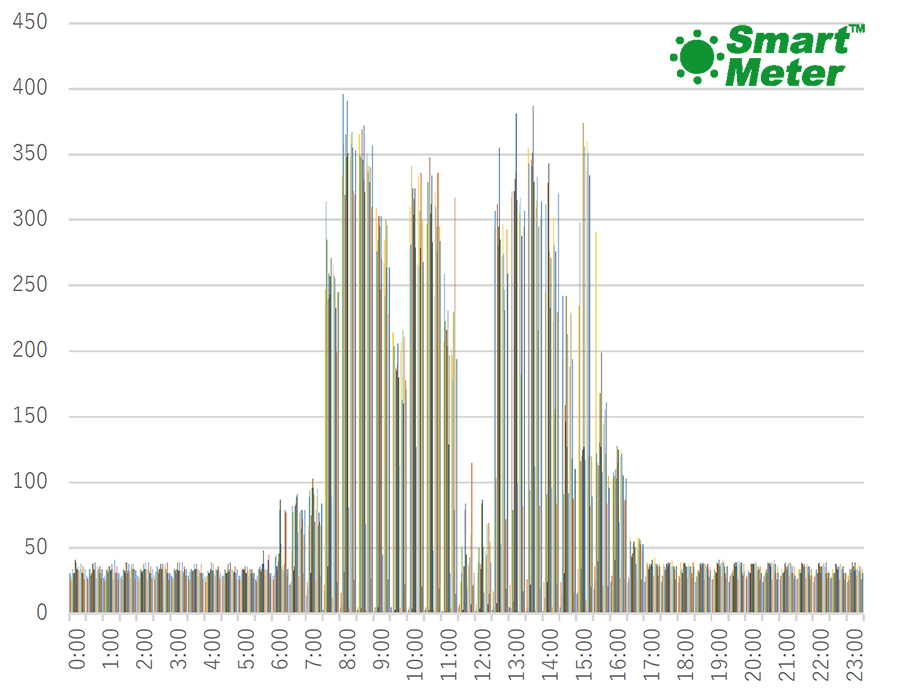1. 賃上げと労働生産性は、なぜ切り離せないのか
労働生産性の国際比較2025が示しているように、賃金水準と労働生産性は密接に結びついています。 付加価値が増えないまま賃金だけを引き上げれば、企業は利益を削るしかありません。 逆に、労働生産性が向上し、就業者一人当たり・時間当たりの付加価値が増えれば、 その増分は企業利益、賃金、減価償却費といった形で分配される原資になります。
言い換えれば、労働生産性が上がらない限り、企業が自発的に賃金を引き上げる余地は極めて限定的です。 この前提を曖昧にしたまま「賃上げだけ」を求める議論は、現場の経営実務とどうしても噛み合いません。
本当に必要なのは、賃上げを「コスト」とみなす発想から、 生産性向上によって付加価値のパイを増やし、その結果として賃上げが可能になるという、 経営と現場が共有できるストーリーを持つことだと考えています。
2. 生産性が伸びている国は、何が違うのか
では、世界に目を向けるとどうでしょうか。 2024年時点で、コロナ禍前と比べて実質労働生産性が最も改善している国の1つがトルコです。 トルコは2022年以降、3年連続で50%を超えるインフレに苦しんでいますが、それでも労働生産性は大きく上昇しています。
背景には、低コスト労働力を武器に欧州向け製造拠点が集積していること、 さらにドローンなど高付加価値製造業への進出があります。 ここで重要なのは、これらの国々が「生産性向上」を精神論や改善活動の積み重ねとして捉えていない、という点です。
彼らは国際競争の中で、どこで付加価値を生み出すのかを明確に定義し、 産業構造そのものを変化させています。 一方で日本は、「高コスト・中付加価値」という、国際競争上きわめて不利なポジションに立たされつつあります。
ここから見えてくるのは、生産性を上げるとは、個々の現場に「頑張り」を求めることではなく、 付加価値の源泉そのものを設計し直すことだという現実です。
3. 日本の生産性が上がらない理由――TPSの限界と前提条件の変化
日本の労働生産性がなかなか向上しない理由の一つとして、 日本企業がお手本としてきたトヨタ生産方式(TPS)の限界が挙げられます。
TPSは、ムダを徹底的に排除し、「ジャスト・イン・タイム」と「自働化」を二本柱として 品質と効率を両立させてきた偉大な生産システムです。 しかし、このTPSが確立された時代は、人口が増え、労働力が豊富で、デフレ基調が続いていた時代でした。
現在の日本は、少子高齢化による慢性的な人手不足、アフターコロナ禍での供給制約、円安インフレという環境です。 この前提の変化のなかで、「ムダを削る」こと自体が、必ずしも生産性向上につながらなくなっています。
TPSが苦手とし始めているポイント
- ジャスト・イン・タイム:在庫を極限まで減らせば、サプライチェーン分断やエネルギー制約に極めて脆弱になります。
- かんばん方式:需要変動が激しい環境では、調整コストがかえって増大しやすくなります。
- カイゼンや5S:現場維持や微調整には有効ですが、付加価値そのものを増やす活動にはなりにくい側面があります。
まとめると、TPSは今でも効率化には非常に強い仕組みですが、 新しい付加価値を生み出す仕組みとしては、前提条件の変化に直面している段階にあると考えています。
4. トヨタは変わっているのに、多くのTPSフォロワーは追随できていない
ここで強調したいのは、「TPSそのものが古くなった」のではないという点です。 むしろトヨタは、環境変化に応じてTPSを絶えず更新してきた企業です。 問題は、多くのTPSフォロワーが、その変化に追随できていないことにあります。
1)「ジャスト・イン・タイム」から「ジャスト・イン・ケース」へ
コロナ禍で顕在化した半導体不足や物流混乱を受けて、トヨタは重要部品については 戦略的在庫を持つ方針へと明確に転換しました。 これは、在庫を単なるムダとみなすのではなく、有事のレジリエンスを確保するための投資として位置づけ直した動きです。
しかし、多くのフォロワー企業では、いまだに「在庫削減=善」という単純なスローガンだけが残り、 供給リスクを経営課題として設計し直すところまで到達していません。
2)評価軸が「効率」だけのままになっている
アフターコロナの世界では、コスト効率だけでなく、止まらないことそのものが競争力になっています。 トヨタはTPSを「効率最大化の道具」から、「レジリエンスを内包した経営システム」へと再定義しつつあります。
一方、日本の多くの製造業では、依然として「効率=正義」という評価軸が支配的で、 レジリエンスを数値化し、投資判断に組み込む文化が十分に根付いていません。
3)デジタルTPSと一次データの落とし穴
2025年現在、TPSはAIやデータ技術と融合した「デジタルTPS」へと進化しています。 しかし、AIやデジタル技術は一次データの質がすべてを左右します。
多くのフォロワー企業は、TPSの「用語」や「見た目」だけを導入し、 データ取得・検証・原本性の担保といった基盤整備を後回しにしてきました。 その結果、「デジタル化したつもりだが、生産性は上がらない」という状態に陥ってしまっています。
結局のところ、問題はTPSそのものではなく、前提条件が変わったのに、 評価軸と仕組みをアップデートできていない側にあるのだと考えています。
5. 日本語という「構造的な制約」――暗黙知とデータのあいだ
もう一つ、見過ごされがちな要因があります。それが日本語という言語の構造です。 日本語は文脈依存が強く、主語が省略され、曖昧さを許容します。 人間関係を円滑にするうえでは優れていますが、ロジックの明確化や構造化には向きにくい側面があります。
生産性向上とは本来、
- 何が付加価値を生んでいるのか
- どこで価値が失われているのか
- どの工程に資源を集中すべきなのか
を明確に言語化し、数値で管理する行為です。 しかし日本企業では、「暗黙知」「現場感覚」「阿吽の呼吸」が尊重されるあまり、 生産性を定量的に議論しにくい構造が温存されてきました。
これは、AIやDXが期待通りの成果を出せない理由とも深く結びついています。 言葉とデータのあいだにあるギャップをどう埋めるかが、これからの生産性向上にとって重要なテーマになっていくはずです。
6. 次回へ――「改善」から「再設計」へ
ここまで見てきたように、日本企業が生産性を取り戻すためには、 TPS的な「改善の積み上げ」だけでは不十分です。 付加価値の源泉そのものを再設計する発想へと、経営も現場も一緒にシフトしていく必要があります。
次回は、「なぜ日本企業は“生産性を測れない”のか」というテーマで、 平均値・工程管理・一次データの欠如がもたらす経営判断の歪みについて掘り下げていく予定です。
生産性向上を「精神論」や「働き方改革」に閉じ込めず、 事業構造とデータの両面から設計し直すためのヒントを、引き続き整理していきます。