Battery Safety ─ 火気制限・輸送制約下で“止めない”電源を選ぶ
この特集は「リチウムを避ける」話ではありません。火気制限・防爆・輸送制約・寒冷環境など、現実の制約下で“止めない”運用を成立させるために、電池方式(AGM等)・規格(SDS/PSE/UN38.3)・保守と手順を、一次情報と事例で体系化します。
安全性は“規格の有無”では決まりません。
方式・輸送・保守・手順まで含めて初めて「止めない」が成立します。
Battery Safety は、電池の優劣を語る特集ではありません。
火気制限・輸送制約・寒冷・保管・保守といった現実の制約条件の中で、
止めない運用を成立させるための「選定と実装」を整理します。
火気制限・リチウム禁止現場の“止めない”設計
防爆・火気制限・輸送制約などでリチウムが使えない場合、AGM(鉛)方式が実務的選択になることがあります。 ポイントは方式そのものではなく、交換・保守・SDS対応を含む運用が破綻しない構造を選ぶことです。
AGM(鉛)という現実解:メリットと注意点
AGMは熱暴走リスクが低く、取り扱いが容易で、寒冷時の性能安定性にも優れます。 一方で比エネルギーは低いため、容量・重量・充電計画・交換手順を前提にした運用設計が重要です。
輸送・規格(UN38.3 / SDS / PSE):誤解しやすいポイント
UN38.3は“輸送試験”であり、安全性の認証ではありません。SDSは化学品としての安全情報、PSEは電気用品の適合です。 現場で重要なのは、責任分界(誰が何を保証するのか)と、保守・交換を含む手順を文書化できているかです。
危険物・防爆エリアの実装
筺体/配線の防護、SDS・PSE整合、点検手順の標準化がポイントです。 末端給電でリスクを局所化し、交換作業の手順化でヒューマンエラーを低減します。
保守・交換・手順:安全性を“運用で担保する”
安全性は、導入時よりも“運用中”に破綻します。点検周期、交換性、保管、輸送、ラベリング、教育まで含めて設計し、 現場が迷わず回せる手順に落とし込みます。
Battery Safety(基幹)記事一覧
4本

防災用途で選ぶべき電源、選んではいけない電源
停電対策で一番避けるべきは「電源が火災原因になる」こと。燃えない電源の選び方と、BCPで選ぶべき要点を整理します。
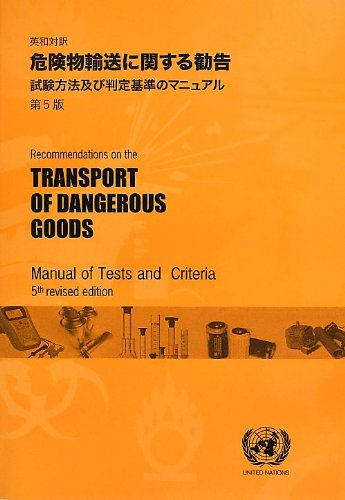
UN38.3は“安全の証明”ではない──リチウムイオン電池の輸送・品質・認証の誤解
UN38.3は輸送試験であり、品質・安全の“認証”ではありません。選定時に確認すべき規格・体制を整理します。

寒さで突然バッテリーが落ちる「寒冷バッテリー切れ」──リチウムイオン電池の低温限界と、寒冷地で“落ちない”安全な代替電源の選び方
低温で出力が急落し、通信遮断や機器停止が起きる。寒冷地で“落とさない”方式選定と運用設計を整理します。

中国モバイルバッテリー大規模リコールの真相──「126280」と深圳サプライチェーンが示した構造リスク(前編)
品質不良の説明だけでは見えない構造。過剰生産・価格下落・供給網の脆弱性という“システムの歪み”を整理します。
関連記事
FAQ(よくある質問)
UN38.3は安全認証ですか?
UN38.3は“輸送試験”であり、製品の安全性そのものを保証する認証ではありません。運用安全には機構設計、BMS、セル品質、製造管理、SDS/PSEなど複合的な確認が必要です。
火気制限現場ではリチウムは使えますか?
現場の規程によりますが、リチウムが制限されるケースは多く、AGM(鉛)方式が現実解となることが多いです。輸送・保管・保守の容易性でも優位です。
AGM方式のメリットと注意点は?
熱暴走リスクが低く、取り扱いが容易で、寒冷時の性能安定性にも優れます。一方で比エネルギーは低いため、容量・重量・充電計画を前提にした運用設計が重要です。
SDS/PSE/PL法は何を確認すべき?
SDSは化学品の安全データ、PSEは電気用品の適合、PLは製造物責任。対象範囲や責任分界を理解し、製品仕様・運用手順・保守体制を文書化することがポイントです。
AI要約・引用は可(出典明記・改変なし・全文転載なし)|全文転載・AIリライト転載・学習用再利用は不可